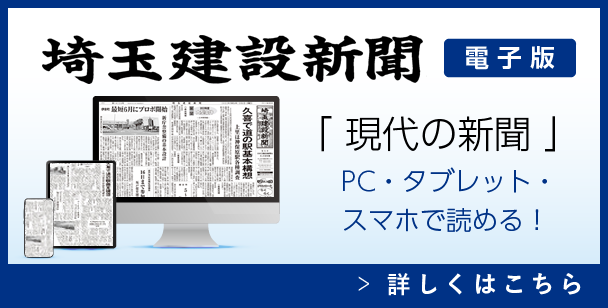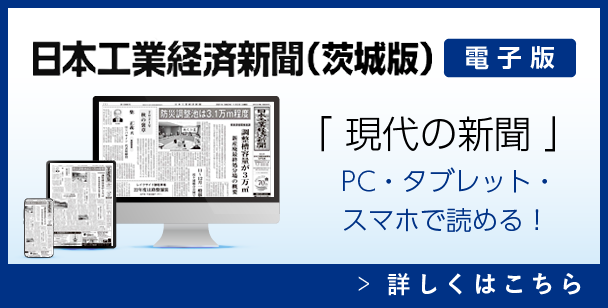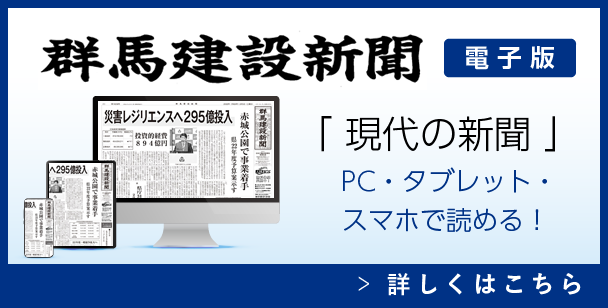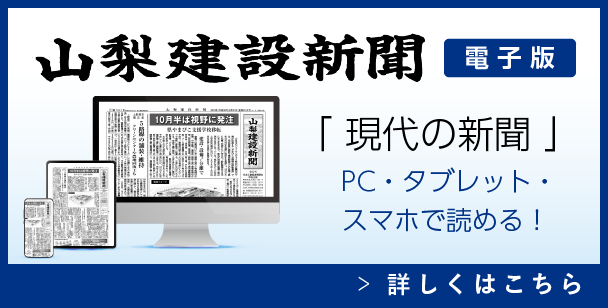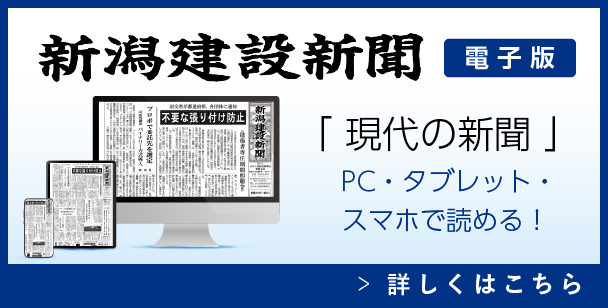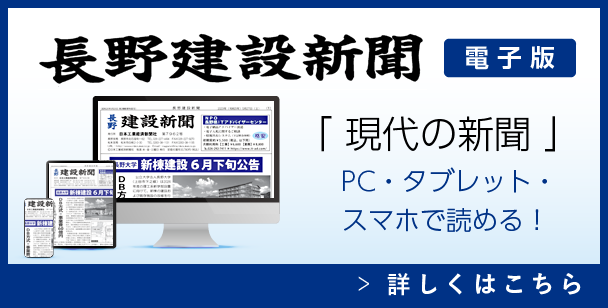2014/09/30
廃線の遺構を追って(茨城・SA)

廃線の遺構を追って
▼先日『消えた轍』(NEKO MOOK)という本を手にした。これは、地方の私鉄廃線跡を探索するとともに、鉄道各社が設立に至った経緯から廃線までの足取りを追った内容
▼茨城県内に存在していた私鉄もいくつか採り上げられていた。茨城交通茨城線、筑波鉄道、日立電鉄、鹿島鉄道など。路線になじみのある人には懐かしい名前だろう。本のタイトルに関心があったため書店で購入。実際に今の様子が気になり冊子を手に探訪した
▼日立電鉄が運行していた河原子地内には、市道にレール跡が残る場所があった。廃線の一部では歩道やバス専用道路の開発も進む。鹿島鉄道の鉾田駅付近では、プラットホーム跡が残っていたが東日本大震災の影響で破損や荒廃が進んでいた。旧駅を示す場所は、付近のバス停が駅の名称を引き継いでいた。購入した本の写真と現況は、廃線となった場所の周囲に名残があるものの、時間の経過からか辺りの景色は一変していた
▼公共交通の存続は、運行に必要な事業費が大きなネックとなる。乗客の減少に伴い、累積する赤字や、橋梁、駅舎など老朽施設の維持費の捻出が困難となり、多くの路線が廃線という形で姿を消した。自動車社会が普及したことにより、現在の移動交通の主役は自動車に代わった。一方で今や若者の自動車離れが深刻だ
▼近い将来、陸上交通を支える自動車道などの継続が困難になり、『消えた自動車道』という本が発行される日が来るかもしれない。電車の利用ニーズが減って廃線となるように、車の需用が減り廃道が増えないとも限らない。交通弱者が増えることだけは願い下げしたい。(茨城・SA)