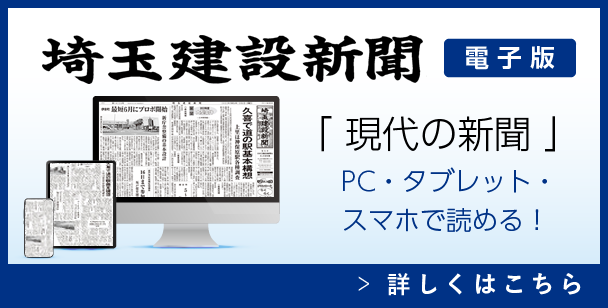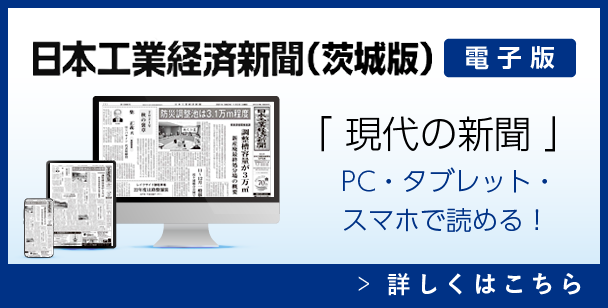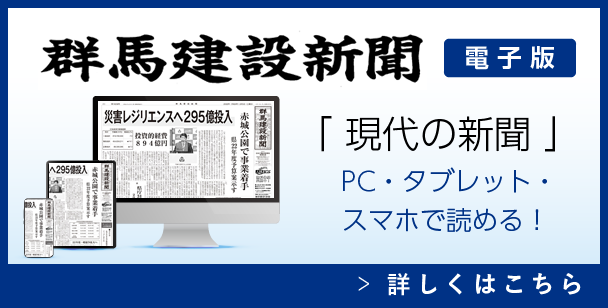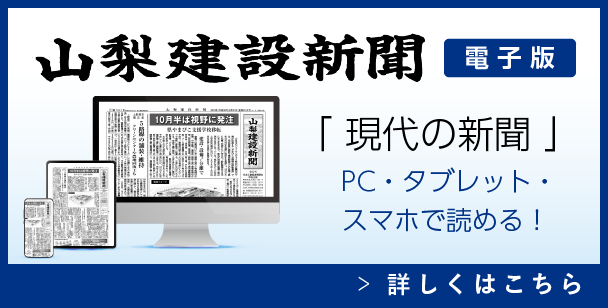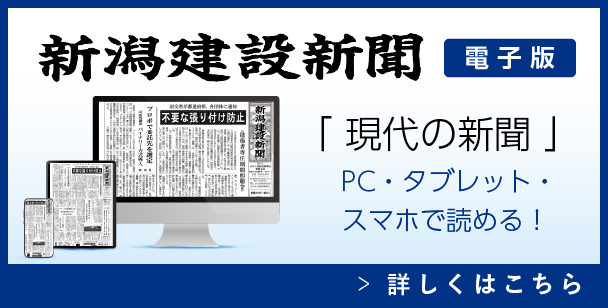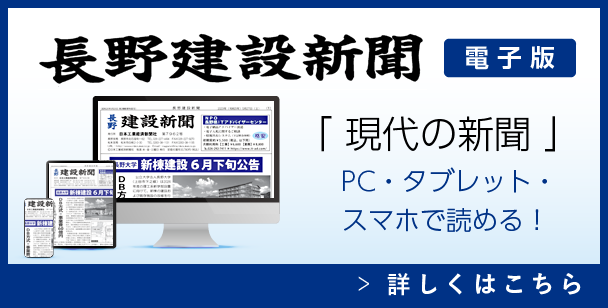2019/11/30
明確化できないもの(埼玉・UT)

明確化できないもの
▼「喉元過ぎれば熱さを忘れる」。困難に苦しんだことも、過ぎ去ってしまえば忘れてしまうことを指す。しかし東日本大震災にように忘れてはならない熱さもある。このことに異論のある方は少ないと思う。ただ、自身の日常を振り返ると反省する点は多々ある
▼10月に各地で甚大な被害をもたらした台風19号は、図らずも公共事業や地域建設会社の重要性を再確認することになった。普段は公共事業の必要性を全く論じず予算を投入することに批判的だった媒体も、今は治水の重要性を繰り返し指摘している。しばらくすればまた公共事業批判に戻るのだろうが、結局繰り返しているだけのように感じる。群馬の八ッ場ダムも、一時は建設=悪、中止=善といった風潮が確かにあった
▼今年の台風による埼玉や千葉の土砂災害発生件数は全国でも上位となった。これまで土砂災害が極めて少ない県という見方が定着していたが、特に根拠のない思い込みのようなものだったのだろう。ハードとソフト両面で、これまで以上の対策を講じてほしい
▼地元に本社があり、重機も人材も近くにあることのありがたさを再確認した発注者の話を聞いた。全国大手の支店があっても、営業マンと事務員が大半だとすれば、即時の災害には対応できない。地域の仕事は地元企業に発注して、健全経営でこれからも存在し続けてもらう必要がある
▼その代わり、県土が災害に見舞われたときには「地域の守り手」として緊急出動してもらう。この関係性は、経済原理や経営論でも合理的に説明できない。またあえて明確化する必要もない特殊なもののような気がしてきた。(埼玉・UT)