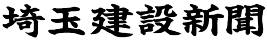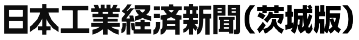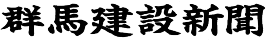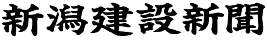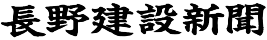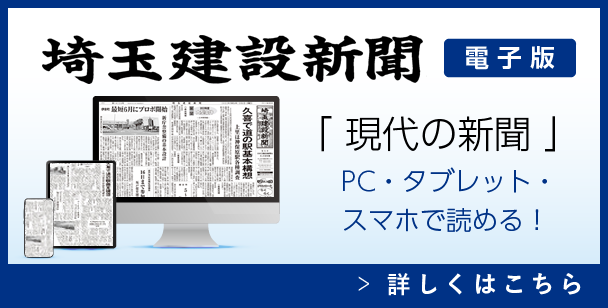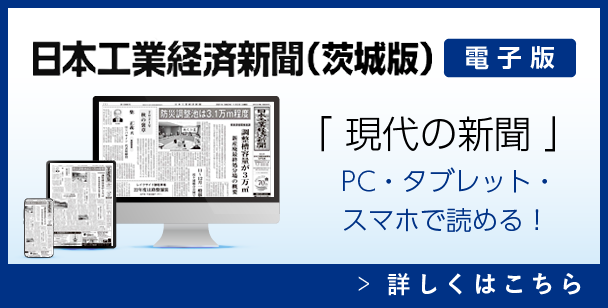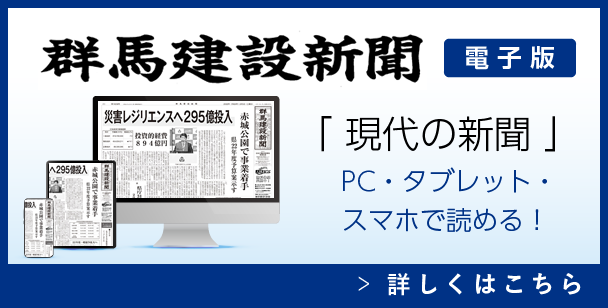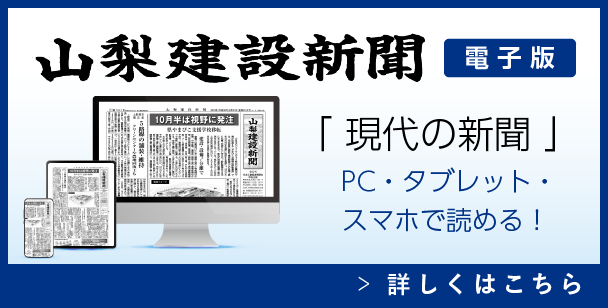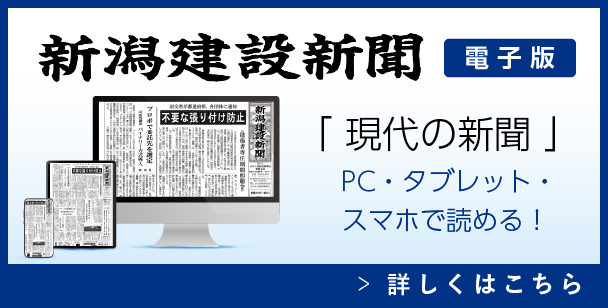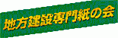2006/11/20
文章の感動は冒頭に多い(甲・SY)

▼秋晴れの日曜日の午後。窓から見える細切れの雲の形が「読書の秋」と書いてあるように見えた。「そう言えば、この頃本を読んでいなかったな」とつぶやく。あれこれ本棚を探し、結局これまで何度も読んだ川端康成の『雪国』を手に取る。「国境の長いトンネルを抜けると雪国だった。夜の底が白くなった」
▼小説が面白いか面白くないかは簡単に言うと、その書き出しで決まる、とある有名な文芸評論家が言っていた。確かに、冒頭部分で「はっ」とすると、あっという間に小説の世界に引き込まれてしまう。短編にしても、長編にしても、書き出しの巧拙が最後まで読者を引っ張るか否かを左右するのであれば、小説も本質的に俳句や短歌や詩と同じヘッドライン文学の一変型なのだろう
▼試みに、冒頭部分が印象的な小説をいくつかあげてみる。「我輩は猫である。名前はまだない」。漱石のこの小説はまぎれもなく、タイトルと冒頭が完全一致の傑作である。「朝、食堂でスウプを一さじ、すっと吸ってお母様が「あ」と幽かな叫び声をおあげになった」。『斜陽』。終戦直後の日本の脱力感が凝縮して表現されている
▼「幸福な家庭はみな似通っているが、不幸な家庭は不幸の相もさまざまである」。『アンナ・カレーニナ』。その後の大長編の展開を予感させる文章だ。英国ファンタジー文学の名作「トムは真夜中の庭で」は冒頭部分で大邸宅の1階ホールの古い大時計が13回時を打つ。読者を異次元に誘い込む合図
▼ここまで書いてきて、冒頭の文章がすばらしいのは「古典」と気づいた。文章修業をするのであれば世界の古典を読むべきか。(甲・SY)