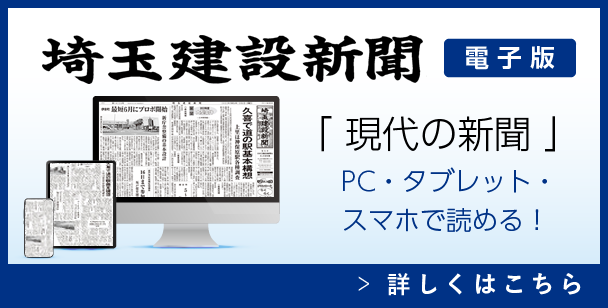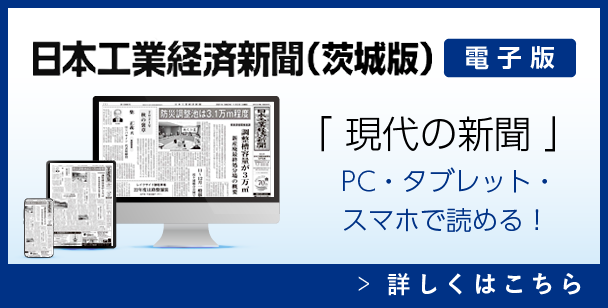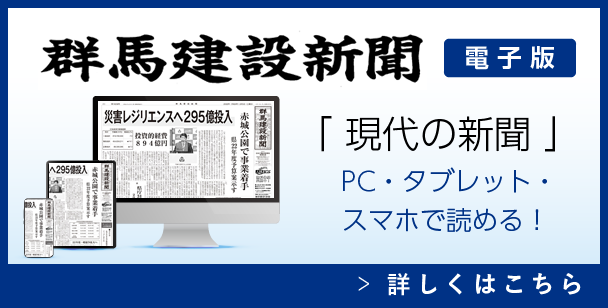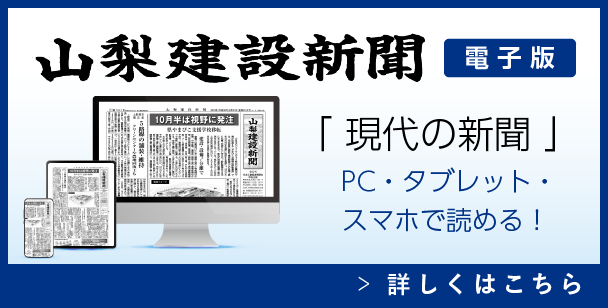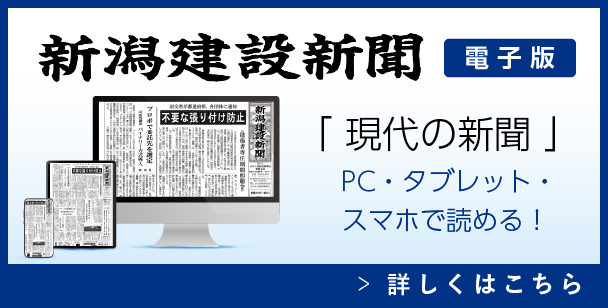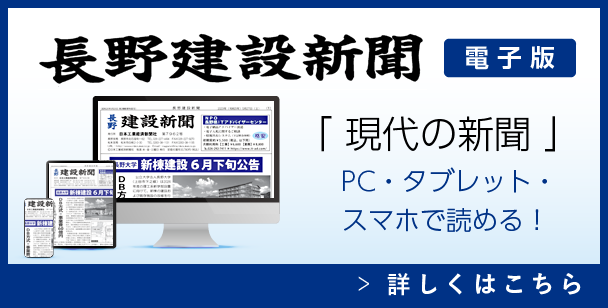2012/06/30
団塊の世代を現場へ(東京・UT)

団塊の世代を現場へ
▼国土交通省関東地方整備局の組織は本局(さいたま市・横浜市)のほか、51の事務所、133の出張所から構成されている。4月6日現在の職員数は4175人。本局勤務992人、事務所勤務3183人となっている。このうち技術系職員は、本局に613人、事務所は2056人。
▼直轄事業は1950年代に直営から請負に転換した後、委託化がどんどん進んだ。現在では「測量から図面おこし、設計・積算までほとんど外注化され、自らの手・足・頭で作業せず、口先で業者に指示する業務形態」と自嘲する声も関係者にはある。
▼同局では12年度、新たに「第三者による品質証明」を試行する。受発注者ではない第三者が現場で出来形・品質を確認し、受発注者双方に品質証明を行うもので、監督・検査のあり方にも大きく関わってくる。国交省本省では、将来的に大半の工事でこの仕組みを取り入れることも想定しているようだ。
▼監督と検査の兼職は禁止されており、第三者導入でも肝になる部分。ただ、近年試行してきた「施工プロセスを通じた検査」において、通常は監督業務の中に含まれる確認行為を、検査業務として実施するというロジックを確立。同様の考え方で、第三者からの「品質証明書の確認による検査」で、工事代金の支払いにも対応する。
▼第三者には品確技術者など、国交省や地方自治体、ゼネコンOBを起用する構想。本当に現場を熟知した団塊の世代の技術屋を、ものづくりの前線に呼び戻す。賛否両論あるようだが、公務員数の大幅削減という厳然たる事実の中で、それでも現場を動かしていくための一手ということだろう。(東京・UT)